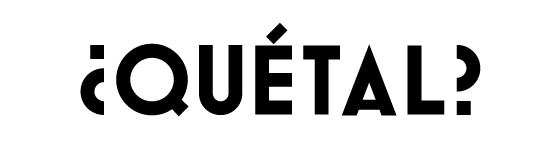テオティトラン・デル・バジェ織物小史 II 氾濫する色
4|狂乱の化学染料時代(1950〜1970 年代)
第二次大戦後、国土の被害もなく戦勝国となったアメリカは空前の好景気に突入する。メキシコを縦断するパンアメリカン・ハイウェイが完成すると、人も文化も貨物も一気に動き出した。フォルクスワーゲンのタイプⅡに乗った米国の若者──ビートニク、ヒッピー、サーファーたち──は、ティファナからメキシコ国道190号線を南下し、オアハカの谷間に“理想郷”を見つける。彼らが求めたのは安宿とメスカル、そして壁に掛ければすぐに「異国のアート」になるラグだった。
いつの時代もそうであるが、歴史の浅いアメリカにとってメキシコは「(実在しない)過去の風景」としてのノスタルジー、「異文化の魅力」としてのエキゾチシズムという両面を持つ対象であり、多くの人々を惹きつけてきた。
当時、村の職人は一軒につき 3~4 台の織機を稼働させ、注文表に合わせてサイズを変え、コチニールではなくアニリン染料で蛍光色を出した。煮出し 15 分、媒染なし、乾燥 1 時間──天然染の手間が一週間なら化学染は半日。ロサンゼルスの輸入業者は「マゼンタをもっと派手に」「ターコイズを濃く」と色指定を送り、半年で 1,000 枚単位のロットを組んだ。村の若者は農地を離れ、手にした現金でピックアップトラックを買い、隣村へ染料を売り歩いた。
しかし光沢のあるネオンピンクは 3 年で褪色し、強アルカリ排水は川底のザリガニを白く変えた。“色は売れるが文化が抜ける”──長老たちの懸念は、次の世代の静かな反発につながる。
5|天然染料リバイバルとグローバル評価(1970〜1990 年代)
転機をつくったのがバスケス家・メンドーサ家・バウティスタ家をはじめとする数世帯の先駆者たちだった。以下では、その中心人物と具体的な功績、そして複数の要因が重なって起こった天然染料リバイバルを整理する。
バスケス家-イスアク・バスケス・ガルシア
8 歳で父と祖父から腰機を教わり、70 年以上「ウールを紡ぎ、草木を煮る」生活を続ける。「私はたぶん織機で死ぬだろう」と語る通り、今も毎朝 6 時には工房に立つ。
羊毛の洗浄・カーディング・紡績・染色・織りまで 100 % 手作業。5 人の娘が洗いとカード、3 人の息子が染めを継承予定で、「家族の手が入らない工程は一つもない」と言い切る。1960 年代、村からコチニールの知識が消えかけたころ、画家ルフィーノ・タマヨがペルー産虫体を、同じく画家のフランシスコ・トレドがインディゴを運び込み、バスケスが色出しを託された。
彼は伝統的なメタテ(玄武岩のすり鉢)で虫を粉砕し、レモン汁と煮沸時間を変えて 20 以上の赤を作る。コチニールは「色の王様」、インディゴは「夜明け前の空」と呼ぶ。鉱物顔料Museo de Rocaや灌木Huisatcheも愛用する。
専門は古代サポテコの象徴体系。グレカやダイヤモンドに、生命と死を意味する二重螺旋を重ねる。「一枚ずつに私の手と心と考えが入る。手だけではなく、目と足と鼓動が必要だ」と語る。
1968 年ルイジアナ州での個展、1970 年メトロポリタン美術館展示で米国市場に天然染を紹介。近年もサンタフェ国際フォークアート市場で完売し、「芸術は国境を持たない」と言う。
サポテカ族の文化伝承にも気を配り、死者の日には亡き妻マリアのため祭壇を飾り、サトウキビのアーチやロウソクの意味を来訪客に説明。「タペテは祖先との会話。その声を次世代が聞けるようにしたい」と言う。
バスケスは、化学染が席巻した時代にインディゴとコチニールを再解釈し、天然染価値の再評価に火をつけた点火役であった。その炎がメンドーサ家やバウティスタ家の革新を照らし、70-90 年代リバイバルの礎になったのである。
メンドーサ家-アルヌルフォ・メンドーサ・ルイス

Image: Arnulfo Mendoza, photographed by Alejandro Linares Garcia, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
テオティトラン・デル・バジェ出身のアーティストで最も有名なアルヌルフォ・メンドーサ・ルイスは天然染タペテをサポテコ伝統と近代美術を接続させ、ファインアートの領域に押し上げた。
父エミリアーノが 1970 年設立した工房MENDOZAの長男として生誕。9 歳で腰機に触れ「糸の張力と色は父から、呼吸の合わせ方は祖父から習った」と語る。
1972–74 年にはオアハカ州立大学ベニート・フアレス校(UABJO)美術学部で構成・配色を専攻。ここでメキシコ北部のサラペ縞に興味を持ち、「縦ストライプ×グレカ」という後年のシグネチャーを着想した。
彼の革新的な技法は以下の通り。
- シルク緯糸の導入。経糸ウール×緯糸シルクの二重組織で光を取り込み、タペテに“布の鏡面”を生んだ。
- ミニマル余白。サポテコの濃密なグレカを片側に寄せ、残りを無地で抜くレイアウトは、ロスコのカラーフィールドからヒントを得たと述懐。
- 天然染への回帰。イスアク・バスケスが再興したコチニール/インディゴを、媒染温度とpHを数値管理しつつ“デザインとしての色面”に昇華させた。
作家活動のみならず、文化振興にも貢献した。1974年に画家ルフィノ・タマヨらとTaller Rufino Tamayoを設立したのを皮切りに、1975年にロサンゼルス・オーティス美術研究所企画で、米国 25 名の現代作家タペストリー制作を監修、1980年には1年間パリで絵画制作を行うなど国境を超えた活動を行った。1993年には日本の国際芸術プロジェクトに参加し、彼の作品2点が東京の最大の公共美術コレクションに収蔵された。
また元妻メアリー・ジェーン・ガニエとギャラリーを共同設立。地元職人のセールスを支援し、オアハカ随一のキュレーション拠点へ成長させた。
また教育者として ワークショップ受講生は 1987–2010 年のべ 600 名超。弟ヤコボや息子ガブリエルを含む次世代に配色理論とシルク技法を伝授。
こうした活動が評価され、1996年にフンド・クルトゥラル・バナメックス(Fundación Cultural Banamex)からメキシコ民芸の「グラン・マエストロ」(偉大な巨匠)の一人に選ばれ、2001年にはエル・インパルシアル紙からチマリ・デ・オロ(黄金の盾)を受賞した。
惜しくも2014年3月7日に59歳で心臓発作により急逝したが、家族工房の伝統を近代美術の色面構成で再構築し、海外での活動とギャラリー運営で市場に橋を架け、天然染料とテオティトランの評価を世界水準へ引き上げた功績は今も称賛の声が絶えない。
バウティスタ家-デメトリオ・バウティスタ・ラソ
デメトリオ・バウティスタ・ラソは、オアハカ州テオティトラン・デル・バジェ出身のマエストロ。両親ガスパール・バウティスタとイレネ・ラソのもとで幼少期から織機を踏み、現在は妻マリベル・アラベス・バスケス、子どもたちジェシカとビクトルを含む80 名超の拡大家族で工房を運営している。
彼はいわば染料オタクとしての探究を深めている。 雨季明けの高地牧草地で花・苔・樹皮を少量ずつ採取。「採り過ぎは未来を奪う」と語り、乱獲を戒める。鉱物顔料も実験対象。石臼で粉砕し、pH をリトマスで測定しながらウールに重ね染めする。
天然染めの代表的な染料であるコチニールとインディゴに関しても研究に余念がない。その深さは、かつて 70 株のノパール(サボテン)でコチニールの虫を飼育したが、「織物師なのか農家なのか」と自嘲するほど。 その結果はレモン汁と加熱時間を変え、赤〜オレンジ 15 段階を作る技法を公開ワークショップで見れる。
デメトリオは 1990 年代半ば、緑の 12 段階グラデーションを初披露した。当時、市場で緑ラグは“売れない色”と見なされ「気が触れたのか」と嘲笑されたが、現在では代表作となり海外顧客の指名買いが絶えない。
古代サポテコのモチーフを好み、教会に転用された遺跡石材の“グレカ”文様、稲妻、ダイヤモンド、生命の樹などを再構築。
村への州道沿いに石造の工房・レストラン・宿を併設。来訪者は即興レッスンで染料鍋をかき混ぜ、モーレを味わい、ラグを選ぶ“住み込み体験”が可能。
テニスコート大のラグをロサンゼルスへ納品した実績が象徴するように、注文は北米・欧州が中心。
収益の一部を染料植物の再植栽と、若手研修に充当。「市場で成功しなければ森も伝統も守れない」と語る。
デメトリオは、緑系統という未開拓分野を切り開き、採取量制限と再植栽でいち早くサステナビリティを実践した。またホスピタリティ複合施設で“体験型工芸ツーリズム”を確立した起業家などさまざまな側面を持ち、天然染料リバイバル後期の担い手となった。
まとめ
1970〜90 年代のリバイバルは、単一のヒーローによる発明ではなく、複数の作家や国内外のアートシーンが絡み合った現象だった。今日、テオティトラン・デル・バジェの天然染のタペテが、化学染の数倍の価格でも飛ぶように売れるのは、民藝と現代芸術の間にあるものとしてコレクティブル(収集価値のあるもの)として世界的に評価されているからである。それは、ここに挙げた中心人物を含め、大勢が先祖の伝統を守り、拓き、深め、そして受け継いできたからである。